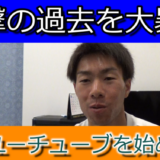12才までのカルシウム効果forジュニアアスリートPR動画
右からランニングシューズの紐を緩める。
この場では周りの音、全てが歓声に聴こえる。
雷管の弾ける音、スパイクのピンがトラックに刺さり抜ける音、アナウンス、そしてスタンド。
エンターテイメントの主役にはいつもその感覚があるのではないだろうか?
全ての要因が選手の背中を押してくれる。
いつも一緒にトレーニングしてくれているランニングシューズに感謝を込めて、スパイクに履き替える。
スタートの合図がしたら、頼りになるのは競技にかけた想いとスパイクだけだ。
【男子100m予選一組】
大きな電光掲示板に一組目のスタートリストが表示されて、次々と選手がスタートの最終調整を行う。
後ろでは他の組の選手がダッシュなどをして、刺激を入れる。
俺は直前に動くことがあまり好きではない。
理由はないが、とりあえずスタートに集中したいからだ。
「オンユアマークス」
スタンドは360度静寂に包まれる。
失敗の許されない瞬間に立ち会うからであろう。
物音ひとつしないヤンマースタジアム長居。
経験者でなければ、その空間が異様であることにすぐに気づくはずだ。
そう、異様なのだ。陸上競技は。
雷管の音が鳴る。
選手たちの一歩目がトラックに衝撃を与え、歓喜が鳴り響く。
その速度は加速を続け、中間疾走へと移行をつなげる。
観客のボルテージは一気に上昇。
先ほどの異様な空間が、一瞬で最高のエンターテイメント空間にいとも簡単に生まれ変わる。
これが陸上競技だ。
そして、観客は絶頂の瞬間をフィニッシュタイマーに委ねる。
そこに感情のリアクションが生まれるのだ。
一組目のタイムは
「10.92」
いきなりのビッグレコードに観客は驚きを隠せない。
それと同時に二組目の期待が膨らむ。
もしかしたら陸上競技の主役は観客なのかもしれない。
感情エネルギーの大きさは、確実に観客の方が大きいだろう。
選手あってのスポーツではなく、観客あってのスポーツなのだろう。
常に選手に価値を付けるのは観客だからね。
選手は主役をどう満足させるかがポイントとなる。
演者は踏み台になってこそ一流。
二組目のスタートリストが電光掲示板に表示される。
「出番だ、行ってきます。」
そう心に語り掛けるように、レーンナンバーが書かれた黄色のボックスの間を小走りで通り抜ける。
前の組の選手がセットしたスターティングブロックを地面から外し、いつもセットしているポジションに直す。
前脚2足と後ろに2マス。
後脚3足と前に2マス。
左右の間隔は他の選手より狭め。
セッティングが終わると、両脚をブロックの面にピタッとつけて20mだけ全力でダッシュする。
そして、会場の雰囲気をスタンドを見ることで感じる。
山谷先生は一人でゴール付近に座っている。
トラックの俺とスタンドの先生。
一瞬だけ目が合う。
「必ず一着で準決勝に進むね。」
山谷先生に言葉では伝えられなかったが、何となく伝わったと思う。
各々が自分のレーンの小さな白いマークで待つ。
それはスターティングブロックの5m間隔を空けたところに位置する。
客観的に見ていたスタートが、主観に変わる瞬間はいつもピストルが教えてくれる。
雷管が弾ける音。
俺は20mで先頭に立つ。
そのままグングン加速を重ねた。
空気が身体を押してくれる。
ここで言う空気というのは会場の雰囲気だ。
全てがメリットに感じられる。
「10.95」
速報タイムを止めたのは、電光掲示板に
【夏木トモヤ】
が一番に表示された。
調子は良かった。
まだ記録は伸ばせると、余力を残したレース展開になったことを、スタンドの山谷先生にアイコンタクトで知らせる。
斜めになった腰ゼッケンを、少し緊張で震えた手で外す。
準決勝には問題なく進めた。
すぐにスパイクを脱いで、シューズに履き替える。
荷物は運営側がゴールまで運んできてくれる。
至れり尽くせりの今大会。
俺は有名選手になった気分でビニール袋の荷物をすぐに回収して、補助競技場に戻った。
山谷先生が日陰を用意してくれていた。
たぶん他の中学校はテントやベンチを用意しているのだろうと思う。
そっちもいいけど、こっちもいい。
結局通過タイムは全体の二番目。
実は通過タイムトップは同じ富山県の藍川セイゴ(アイカワセイゴ)だ。
お互いに何度か県大会の決勝でレースをしてきているが、特に仲がいいわけでも悪いわけでもない。
そして、俺は藍川セイゴに一度も勝ったことがない。
競技にプライドがある選手はどこか素直になれなくて、お互いに認めたくないのは本能だろう。
少しの間、日陰で山谷先生と休憩する。
「いいレースだった、準決勝も楽しんでくるといい」
山谷先生の精一杯のアドバイスを受け取ると俺は軽くうなずいた。
準決勝のスタートリストを掲示板に見に行く途中に、他校の生徒の雑音が聞こえてきた。
「準決勝の組見た?夏木トモヤと藍川セイゴ一緒の組らしいぜ!」
チャンスだ。
ここで自信をつけて決勝に挑みたい。
俺は改めてスタートリストを確認すると
「4レーン夏木トモヤ」
「7レーン藍川セイゴ」
いよいよ準決勝だ。この舞台、誰にも譲らない。
12才までのカルシウム効果forジュニアアスリートPR動画